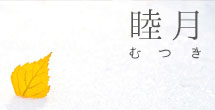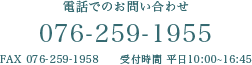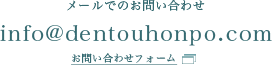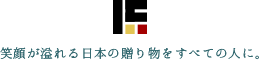古九谷
今日「古九谷風」と呼ばれているものは、数多い古九谷窯の名作のなかでも五彩(赤、緑、紺青、紫)で白磁に絵付けされているものです。他の色絵磁器の産地と比較しても、特徴的な九谷焼の色絵はその大胆なな色使いが特に目立ちます。

花詰
九谷焼の豪華絢爛を代表する画風。磁器全体を花で覆ったデザインは、非常に精密な技術が求められるため、この技法を習得するには十年以上の経験が必要とも言われています。 文字通り、余すところ無く敷き詰められた花々は空間を華やかに彩ってくれます。

本金物
九谷焼は豪華で美しい色彩の焼き物といわれています。そして、本金を使った絵付けは古くからこの地方で贈り物や献上品として親しまれ、好まれていました。金の純度の高い物は年数を重ねてもその輝きが衰えないところから敬老の日の贈り物や新築祝いなどの贈り物として今でも多くの方々に愛されています。

赤絵
赤絵は赤絵の具で人物や模様を書き、所々金彩を加えて全体を埋め尽くす手法です。八郎手や赤絵細描画とも呼ばれています。精密さが求められるこのスタイルでは、筆を満足に扱えるようになるには、10年以上の経験が必要と言われています。現在の飯田屋風の技法を継承する九谷を代表する作家、福島武山氏がいます。

釉彩
釉彩(ゆうさい)は釉薬のグラデーションによる現代九谷焼独特のデザインです。 釉彩は一般的な総称で、このほかにも『彩釉磁器』や『耀彩』とも呼ばれています。彩釉磁器の技法で『国指定重要無形文化財』(人間国宝)に認定された徳田八十吉氏はその独自のスタイルを耀彩(ようさい)と名づけています。

吉田屋
伝統的な九谷の絵柄のひとつで、赤を使わず、主に青、黄、紫、緑の四彩で花鳥山水を描いたもの。背景色として黄色が多く用いられます。文政6年~天保2年(1824~1831)に栄えた再興九谷の窯元。

金彩
金彩とは金箔を貼り付けてその上から釉薬を施す技法です。中でも釉裏金彩(ゆうりきんさい)といった技法が有名で「金箔」や金箔より数倍の厚みのある「ずみ」を貼り付けその上から釉薬を施す技法です。 吉田美統氏は釉裏金彩の技法で『国指定重要無形文化財』(人間国宝)に認定されています。

庄三
庄三風はこれまでの九谷の特徴を画風に生かしながらも、西洋絵の具による中間色を取り入れ、繊細で柔らかい筆調が特徴的。さらには洋風デザインとの混ざり合いが新感覚を生み出し、海外への輸出も盛んになるほどの盛隆をみせた。また、その色彩豊さから「彩色金襴手」とも呼ばれる。

青粒
粒(ちぶ)は絵の具を小さい点に盛り上げて打っていく九谷焼特有の技法です。青や白の絵の具で描かれることが多いため、青粒や白粒と呼ばれます。通常の色絵磁器と異なり、表面の立体的な天の感触が特に好まれています。粒打ちで最高峰の技術の持ち主である仲田錦玉氏は「渦状に粒を打つ」スタイルで独自の世界観を確立した。

銀彩
銀彩とは銀箔を貼り付けてその上から釉薬を施す技法です。釉薬には透明釉や九谷五彩が用いられ、下に貼った銀箔が透き通って見えるようになっています。二色以上の釉薬をあわせて使うことで、より豊かな色彩表現を可能にします。銀箔のデザインや釉薬の色彩、その技法を使い第一線で活躍している中田一於氏は、『石川県指定無形文化財』に認定されているほど。

木米
木米風は素地に赤を塗り、その上から人物をメインに五彩を用いて描いた画風です。このスタイルは伝統な九谷五彩を特徴とする作品のひとつで、赤が特に印象的です。19世紀はじめに開かれた春日山窯(現在の金沢卯辰山に位置する)に京都より招かれた青木木米がはじめた画風のため 木米風と呼ばれるようになりました。

盛
粘性のある絵具で立体的な絵付けを施すのが「盛」の最大の特徴です。焼きあげると絵具が盛り上がった状態で固まり、立体的な表現が生まれます。また、指で触るとなんとも言えない感覚で使う人を魅了する伝統的な技法です。